
✅「自分の会社じゃ許可は難しいかも…」そう思っていませんか?
✅「このままでは、産廃許可が取得できない…」と考えていませんか?
でも、まだ諦めるのは早いかもしれません。「政令使用人」や「令6条の10に規定する使用人」という制度をご存じでしょうか?聞き慣れない言葉かもしれませんが、この制度を上手く活用すれば、御社でも産廃許可の取得が可能になるケースがあります。実際、弊所では「政令使用人の制度」を活用し、東京都の産廃収集運搬業許可を取得した実績があります。
このページでは、許可取得に至った具体的な成功事例とともに、「令6条の10に規定する使用人」とは何かを分かりやすく解説していきます。
依頼内容
| ご依頼者さまの所在地 | 東京都豊島区 |
|---|---|
| 申請先自治体 | 東京都 |
| 廃棄物の種類 | 廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/金属くず/ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず/がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む・限定無し) |
| 依頼内容 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請 |
以前、弊所サービスを利用して、東京都の建設業許可(管工事・電気工事)を取得した事業者さまからのご相談です。管工事・電気工事を請負う際に、どうしても廃材として、産業廃棄物が出てしまうので、東京都の産廃収集運搬業の許可が欲しい。ただ、日本産業廃棄物書類振興センターの講習会を受講し、修了証を取得したのが、役員ではない。
役員以外のものが、講習会の修了証を取得した場合でも、産廃許可の取得は可能か?政令使用人(令6条の10に規定する使用人)の資格で取得することはできないか?
弊所の対応
実は、弊所では過去にも、代表取締役や取締役以外の従業員の講習会の修了証を利用して、東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したことがありました。
この事案では、お問合せを頂いた約1か月後に東京都庁への申請を行い、そのさらに1か月半後に東京都の産廃許可を取得することができました。スピード的には、かなり速いほうだと思います。それだけ、お客さまにも、許可取得の必要書類の提出にご協力をしていただきました。
本来、産廃許可を取得するには、代表者や取締役が日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を取得しなければなりません(講習会は、対面での受講とオンライン受講を選択できるようになっています。また、効果測定のみ試験会場にて行われています。)。しかし、「令6条の10に規定する使用人」を置くことによって、代表者や役員が講習会を受講しなくても「令6条の10に規定する使用人」が受講すれば、産廃許可を取得することができます。では「令6条の10に規定する使用人」とは、どういった人のことを言うのでしょうか?
令6条の10に規定する使用人とは….
難しい言葉ですので「令6条の10」と「使用人」という2つの言葉に分けて考えていきましょう。
「使用人」とは
まず、「使用人」とは、会社と雇用契約を結び、会社に使用されている人のことを言います。「代表者」や「取締役」は、使用人には該当しません。簡単にわかりやすく言うと「使用人」とは、「従業員」「正社員」ということもできるかもしれません。
「令6条の10」とは
この「令」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」を言います。ネットで検索すると条文が出てきますが、条文の理解・精読をしていてもしょうがありませんので、簡単に要約すると
- 本店又は支店
又は、
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集等の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
と理解してみてください。キーワードは、「従業員」「正社員」「本店または支店」です。このキーワードを整理すると、仮に代表取締役や取締役ではない使用人(従業員・正社員)であったとしても、「本店や支店」の代表として産業廃棄物の収集などの業に係る契約を締結する権限を有するものを置けば、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できることになります。
政令使用人に関する証明書
政令使用人(「令6条の10に規定する使用人」)を置く場合には、「政令使用人に関する証明書」を添付する必要があります。今回の申請では、代表取締役・取締役以外の正社員であるAさんを東京本店の長として
- 法令遵守に関する社員教育
- 社員への具体的作業に関する指導・指示
- 収集運搬に関する契約締結権者として、社内折衝、社内調整、最終的意思決定
などの業務を行っている者として「政令使用人に関する証明書」を添付のうえ、東京都庁に提出しました。
令6条の10に規定する使用人の資格を使って、許可を取得したい人へ

「講習会を受けた(受ける)のが取締役じゃない…」そんな場合でも、許可は取れる可能性があります。
弊所で取り扱う産業廃棄物収集運搬業の許可申請のうち、9割以上は代表取締役または取締役の講習会修了証を使用しています。なぜなら、通常はこの方々が、産廃業務に関する契約などの実質的な責任者と見なされるからです。
しかし、会社の事情はそれぞれです。中には、
■ 実務を担っているのは取締役ではない
■ 実際に契約をまとめる担当者は別にいる
というケースもあるはず。そんなときに活用できるのが、「政令使用人(令6条の10に規定する使用人)」という制度です。代表取締役や取締役以外の方に契約締結の権限を正式に与えることで、産廃許可の取得が可能になる場合があります。もし、御社が、「取締役以外の人物が講習会を受けているけれど、許可を取りたい」という特殊な事情を抱えている状況であれば、この記事の内容が、きっと役に立つはずです。
もし「うちの会社の場合はどうだろう?」と少しでも気になった方は、一度、専門家に相談してみるのも良いかもしれません。
代表取締役以外の方の講習修了証で許可を取得したケースも増えてきていますが、申請書の作成や証明の出し方には少し工夫が必要になることもあります。また、行政書士法人スマートサイドでは、実際に政令使用人を活用して産廃許可を取得した事例を多数扱ってきました。そのため、御社の状況に合わせて、産廃許可を申請することが可能です。
相談や質問については、下記のお問い合わせフォームからお送りいただけますと幸いです。フォームからのご連絡であれば、お時間を気にせず送信いただけますので、どうぞご活用ください。ご入力いただいた内容をもとに、こちらからご返信させていただきます。


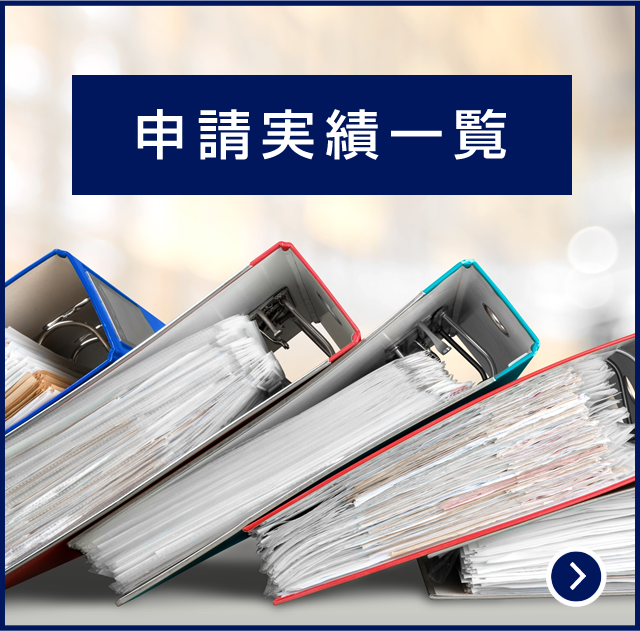

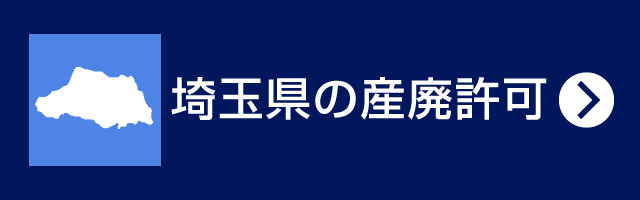


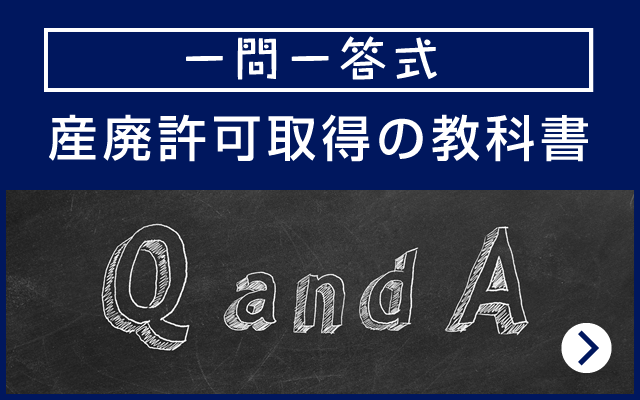
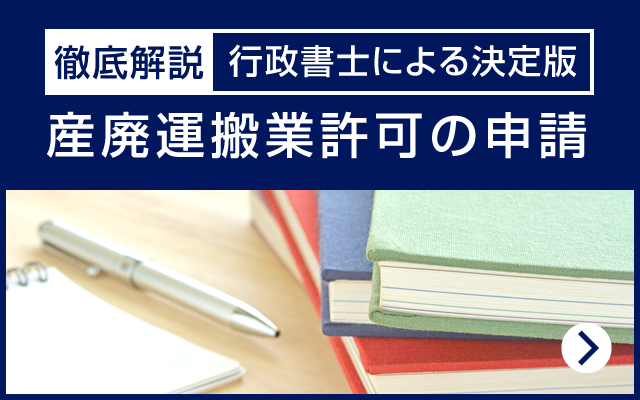
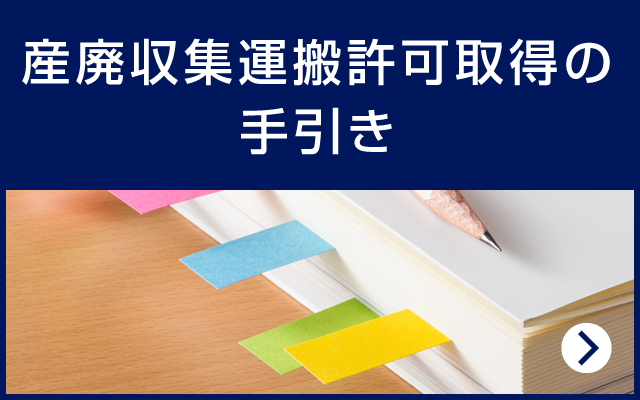
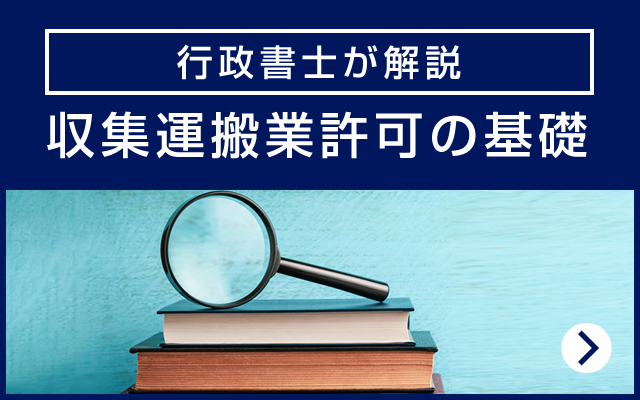

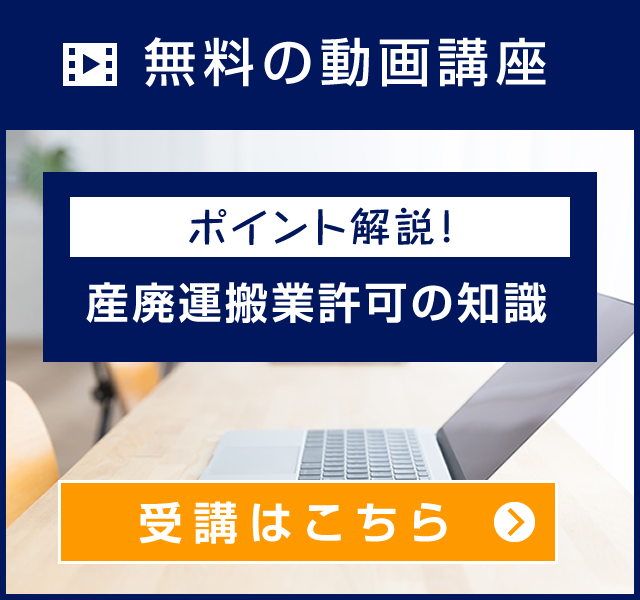
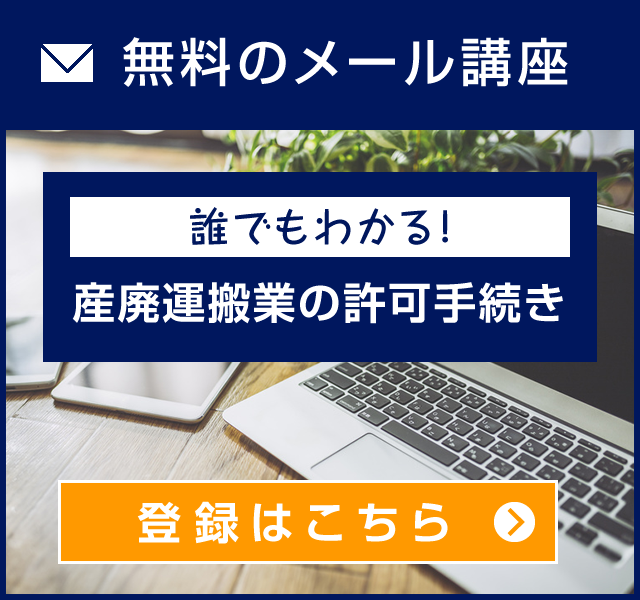
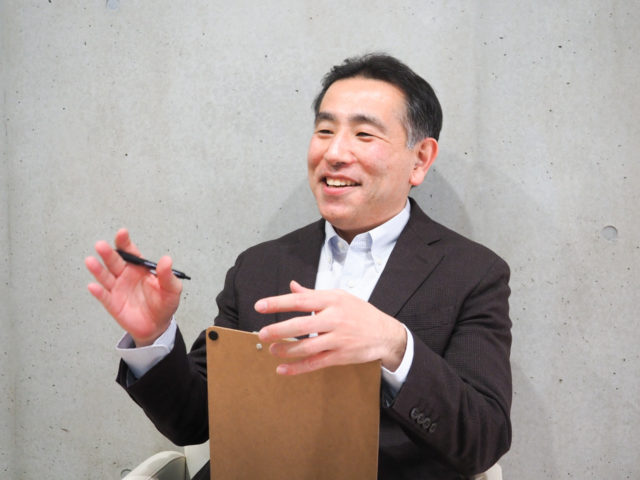 横内賢郎(行政書士)
横内賢郎(行政書士)